こころ
2007/08/17
何十年かぶりに夏目漱石の「こころ」を読みました。きっかけは、1週間ほど前の新聞のコラムに「新潮文庫で発行された8000を越えるタイトルのうち、最も読まれたのは夏目漱石の“こころ”である」とあったことです。記事を読んで、懐かしくなって本棚から取り出してみると、奥付には昭和53年の刷りとなっていました。ちょうど僕が中学1年生。確か夏休みの課題図書かなんかで読んだような覚えがあります。
その時の印象は「よくわからない」「何だこの煮え切らない“先生”と言う人物は」というものでした。記憶に残っているのは、襖に残った自殺した“K”の血痕の描写くらいでしょうか?今読み直してみると実に味わい深い物語なんですが、昭和50年代の中学生にとっては、物語の背景となる“明治”という時代感覚やその時代の倫理観など難解で理解不能なことだったのでしょう。
新聞のコラムにもありましたが、この物語の主人公である“私(明治から大正に移る時代の東大生)”の立場で読むのと、“先生(東大卒、生粋の明治人だが、生業を持たない自由人、人生の影多し?)”の立場で読むのでは全く違った印象になります。例えば、中学生の時はものすごく嫌悪した“私”の父親の病気に際して“先生”が遺産相続の交渉を存命中にやるべきだと勧めるくだりなどは、今なら「そうだよね。若い人にはそういうことを伝えなければ」と思いながら読めました。そんな自分にちょっとびっくりしました。
中学生の自分は精一杯背伸びをして“私”の立場で読もうとしたのですが、それも難しかったのでしょう。今回はかなりの部分“先生”の立場で読むことができたのが、作品を味わえた原因ではと思います。今の学生達はあまり古典を読んだ経験がないようですが、わからないなりにも、10代後半の時期に一度読んでほしい作品です。




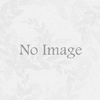
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません